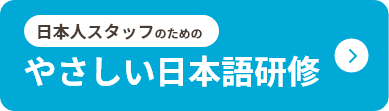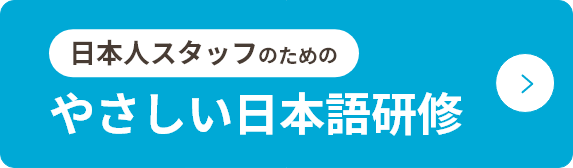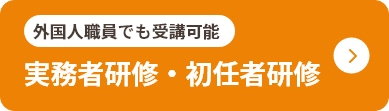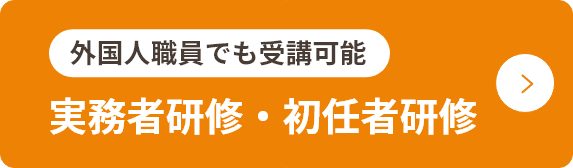2023.11.01
外国人スタッフは人材不足解消だけではない良い影響をもたらしてくれる
社会福祉法人 五霞愛隣会
きららの杜 施設長
小林様

社会福祉法人 五霞愛隣会
きららの杜 施設長
小林様

受け入れには日本人スタッフの理解が必須
定期的な勉強会を開催

人材不足解消だけではない
異文化交流による施設の活性化

長く働いてもらうために
魅力的な環境づくりの必要性
| 創立 | 昭和53年8月 |
|---|---|
| 主たる事務所 | 茨城県猿島郡五霞町元栗橋1563-3 |
| 職員数 | – |
| 外国籍職員数 | 16名(2023年3月末時点) |
| HP | https://www.goka.ed.jp/airinkai/ |


日本人スタッフの戸惑いを解消
外国人介護人材受け入れのきっかけ
日本人介護士の採用が難しい状況が続いていたため、2017年から技能実習制度と合わせてEPA制度を活用して採用活動を始めました。さらに2019年から新たな在留資格「特定技能」が始まり外国人の採用も加速すると思ったので、今のうちから受け入れを行なって備えておこうという気持ちがありました。 (※)EPA:国同士の経済強化を図るための経済連携協定制度のこと。日本はその交流の一環で、東南アジアの国々から介護福祉士の候補者を受け入れている。
受け入れに向け定期的に勉強会を開催
最初は、スタッフから戸惑いの反応がありました。ただ、受け入れまで半年間の準備期間があったので、その間に定期的に勉強会を開いてEPA制度の仕組みや決まり事、実習生が生まれ育った国などについて説明する機会を設けました。 そのおかげで、来日時には職員の理解度は大きく変わっていました。スタッフとの認識をすり合わせることはとても大切ですし、絶対必要なことだと思います。
学習やコミュニケーション面をサポート
必ず日本人が隣にいる状況を作る
最初は、インドネシアの女性スタッフを2名受け入れました。まず基本的な日本語と介護で使う言葉の勉強、介護技術の練習が中心にして、1〜2ヶ月は日勤、あとは早番か遅番に固定して仕事を覚えてもらっていました。まだ日本語がそれほど理解できないうちは、夜勤や遅番のシフトは入れないようにして、必ず日本人が隣にいる状況を作るような体制にしていました。
外国人スタッフの学習モチベーション
外国人スタッフにとって日本語の勉強は非常に重要ですが、自分でモチベーションを保ちながら学べる子もいればそうでない子もいます。それでも、「勉強して国家試験に合格したい」「介護福祉士になったら家族を日本に連れて来たい」などの思いがあるスタッフは、モチベーションを高め続けられていると感じます。外国人スタッフの学習意欲を維持したり高めることができるよう、日常のコミュニケーションも気を配っていますね。
外国人スタッフ受け入れの影響
日本人向けだった研修体系では外国人スタッフはついていけないので、外国人相手でも丁寧に教えていけるように教育マニュアルを見直しました。外国人スタッフはもちろんですが、日本人の職員も業務に対する理解がさらに深まったのではないかと思います。 さらに外国人スタッフがインドネシア料理を振る舞ってもらうイベントなど施設内の行事も華やかになるなど、外国人スタッフを受け入れることで人材不足解消だけではない良い影響があったのは発見でした。

日本人の職員の異文化理解が大切
外国人スタッフを受け入れる上で特に重要なことは、日本人スタッフが他国の文化を理解です。たとえばイスラム教徒であれば、宗教や文化、食べてはいけないもの、ヒジャブをつける理由、お祈りの時間の回数、ラマダンという断食の期間があるなど、様々な情報を最初のうちに伝えておくことが大事ですね。 そのような外国の文化を尊重することは絶対に必要ですし、日本人スタッフの異文化理解がないと一緒に働くことは難しいと思います。その国の表面上のことだけでなく、何を大事にする性格なのか、どんな考えを持っているのか、という内面的なところまで理解してもらえるよう、全てのスタッフに細かく説明していました。説明すればするほど、実際に来日した時のギャップは抑えられると思います。
外国人スタッフにより魅力的な環境を
当施設はポジションが固定されていることが一つの課題だと感じています。相談員やユニットリーダー、介護主任などのポジションは、施設の開設当初から長く働いているスタッフが就いているので、外国人スタッフでも担当できる、新しいポジションの創設も検討しているところです。 今後も外国人スタッフの採用は続けるつもりですし、モチベーションを高く保って長く働いてもらうためにも、そういった人事制度を考えていきたいですね。