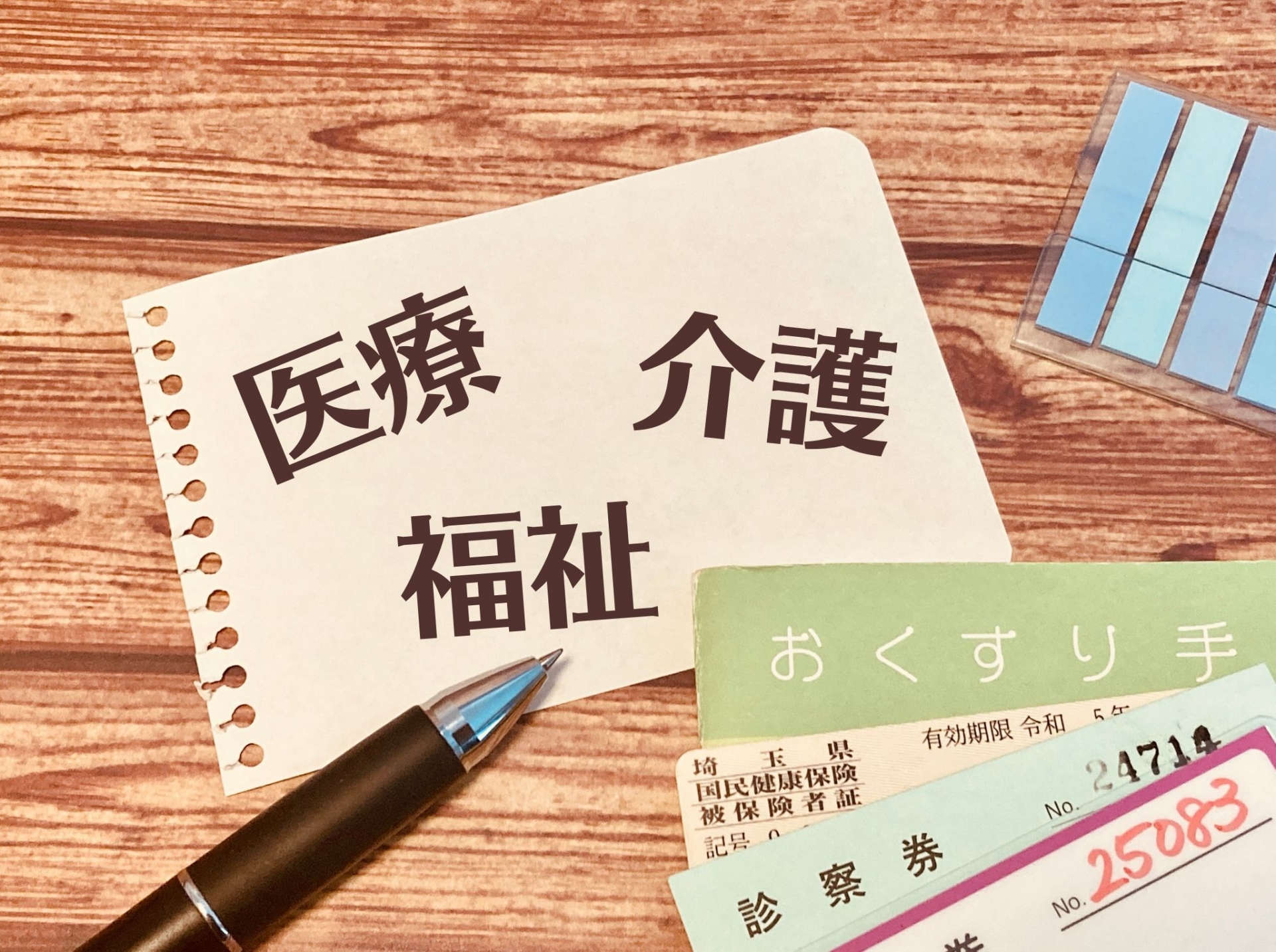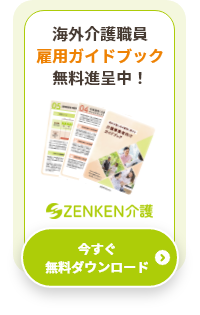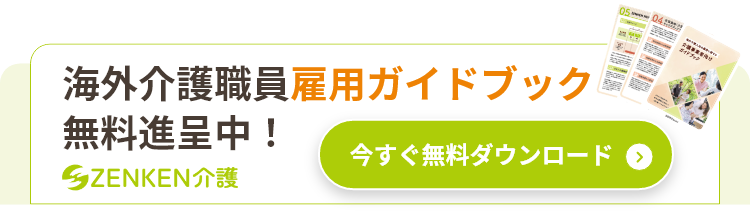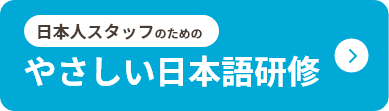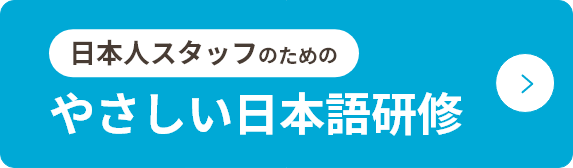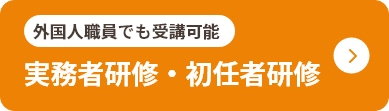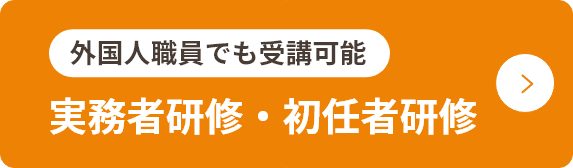外国人を介護職員として雇用できる在留資格の種類と特徴を徹底解説!
2023.11.01

人材不足が深刻化する介護現場において、海外人材は救世主になり得ると言っても過言ではないのではないでしょうか。しかし、海外人材を雇用するのにあたり、どのような在留資格があるのか理解しておくことが必要です。海外人材を介護職員として雇用できる在留資格は以下の4種類あります。
○特定技能「介護」
○技能実習「介護」
○「介護」
○特定活動「EPA介護福祉士候補者」
ここでは、これら4種類の在留資格について、詳しく解説していきます。貴施設で海外人材の受け入れをご検討の採用担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
特定技能「介護」
特定技能「介護」在留資格取得について
特定技能「介護」は、日本での就労を目的とした外国人の在留資格の1つです。介護分野において顕著になっている人手不足を解消するために、導入されました。
特定技能「介護」では、ビザの更新を1年・6ヶ月または4ヶ月毎に行いながら、通算5年まで日本で介護職員として働けます。特定技能「介護」で介護の仕事をする場合、介護福祉士の資格は必須ではありません。その代わり、はじめに特定技能「介護」の在留資格を取得するためには、日本語試験の既定レベルを取得し、介護特定技能評価試験に合格するといった要件を満たす必要があります。
そもそも「特定技能」とは
ちなみに、「特定技能」とは、日本国内における生産年齢人口の減少に伴い、人材を確保することが難しい状況の産業分野に、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする在留資格です。2019年4月から、14業種の特定産業分野で、即戦力となる外国人の就労ができるようになり、介護も特定産業分野に含まれています。
「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は全ての14業種、2号は14業種のうちの2業種が指定されています。介護は「特定技能1号」に該当します。
法務省によると、「特定技能1号」は、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」、「特定技能2号」は、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。
在留期間について
在留期間については、「特定技能1号」では上限が「5年」なのに対し、「特定技能2号」は在留期間の上限がありません。また「特定技能2号」においては、要件を満たすことができれば、家族帯同も可能です。
以下のページでは、特定技能「介護」で海外人材を受け入れるまでの流れやポイント、メリット、注意点をご紹介しています。あわせてぜひご一読ください。
特定技能「介護」による海外人材受け入れまでの流れ
Zenkenは登録支援機関として特定技能介護人材の現地教育から採用、日本語教育、更には「定着」を目的とした国家試験取得まで、あらゆる課題をワンストップで解決します。海外介護人材の受け入れをご検討されている方は、以下のお問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。
技能実習「介護」
外国人の人材を採用しやすい在留資格
技能実習制度は、日本で培われた技能や技術を開発途上国へ移転し、国際貢献を目的につくられました。
外国人が技能実習「介護」の在留資格を取得する際には、学歴や資格などの要件は基本的に求められません。1年目は「技能実習1号」、2~3年目は「技能実習2号」、4~5年目は「技能実習3号」となっており、合計で最長5年の滞在が可能です。
技能実習「介護」は、1993年に創設され、成熟している制度であると言えます。そのため、外国人の人材を採用しやすい在留資格でもあると考えられます。ただし、介護の知識を1から育成しなければならないことから、介護の業務をスムーズにこなせるようになるまでは、時間と手間がかかるでしょう。
「介護」
介護福祉士に合格することが条件
「介護」は、介護福祉士養成学校を卒業し、国家試験の「介護福祉士」に合格することが条件の在留資格です。在留資格「介護」は制度として、2017年9月からスタートしています。在留期間の上限は設けられていないため、ビザの更新を行えば、永続的に日本で介護士として働くことができます。業務の制限もなく、特定技能「介護」や技能実習「介護」の在留資格では、不可とされている訪問系サービスにも従事させられます。
在留資格「介護」の要件
要件として、日本語能力がかなり高いレベルが求められるうえ、介護福祉士の国家試験に合格した人しか取得できない在留資格のため、その数には限りがあり、採用することは容易ではないと言えます。
外国人の介護人材を採用する企業が、介護福祉士養成学校の費用を出すケースもありますが、その場合は、1人あたり数百万円程の負担が必要になることがあります。
特定活動「EPA介護福祉士候補者」
介護施設で働きながら介護福祉士国家資格取得をめざす
EPA(経済連携協定)に基づく在留資格です。日本の国家資格である介護福祉士の試験に合格することを目的に入国し、実務経験を積むために、介護施設で働くことが認められています。
対象となる国籍はインドネシア、フィリピン、ベトナムの3ヶ国のみです。原則4年間の在留期間内に介護福祉士の試験に合格した際は、在留資格が本人の希望により、「介護」または特定活動「EPA介護福祉士」に変更され、介護施設で働くことを条件として、在留期間には上限が設けられず、永続的に日本で働くことが可能になります。
介護福祉士資格取得に関して
介護福祉士資格を取得できなかった場合は、在留期間1年の延長が許可され、もう一度介護福祉士の試験を受験することができます。1年延長した期間中に合格すれば、前述の通り本人の希望により新たな在留資格を選択して変更し、何年でも介護施設で就労することができますが、不合格の場合は帰国をしなければなりません。
4つの介護ができる在留資格のメリット・デメリット
前述で説明した、介護の仕事ができる4つの在留資格のメリットとデメリットを以下にまとめました。
| 制度 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 特定技能「介護」 |
|
|
| 技能実習「介護」 |
|
|
| 「介護」 |
|
|
| 特定活動「EPA介護福祉士候補者」 |
|
|
4つの在留資格のなかで、「介護」と特定活動「EPA介護福祉士候補者」は対象者の人数が限定的なことから、比較的採用しやすい特定技能「介護」や技能実習「介護」を検討されることをおすすめします。
特定技能と技能実習どちらを選ぶべき?
特定技能の特徴
特定技能は、介護の事業所へ配属されると同時に人員配置基準に加えられます。しかし、技能実習で外国人の介護人材を雇用する際には、実習生を事業所に配属した後、6ヶ月間は人員配置基準にカウントすることができません。「人員配置基準に加えられない」ということは、国から介護職員として認めてもらえないということになり、その分の介護職員を雇う必要があるのです。
人手を集める必要がある新設事業所においては、施設が開所した後、3年間は受け入れができない技能実習より、特定技能のほうが優位と言えます。特定技能は新設の介護施設でも雇用が可能です。
また、特定技能は技能実習に比べて、海外介護人材の雇用受け入れ人数枠が大きいことも特筆すべき点でしょう。
雇用の義務についても特定技能は3ヶ月に1回、国へ計画通り業務が遂行されているかどうかを報告するだけで済むため、技能実習より簡素です。
技能実習の特徴
技能実習の場合は、監理団体が国に報告ができるように、毎月、技能実習先の事業者と実習生との面談を個別に行い、出勤簿や賃金台帳を確認して労働基準法違反がないかどうかをチェックし記録します。
一方で、転職が認められている特定技能に比べて、技能実習では転職は原則許可されていないため、費用や時間、手間をかけて育てた人材の流出は最小限に抑えることができるでしょう。
また、技能実習から特定技能へ在留資格を変更することができれば、合計10年間日本で働けます。特定技能の場合は、最長でも5年の雇用期間となるため、5年以上働いてもらいたい事業所にとっては、まずは、技能実習で採用してから、特定技能へ変更するという方法が考えられます。
以上のことから、特定技能と技能実習のどちらが相応しいのかおすすめする事業所のケースをまとめると以下のようになります。
| 特定技能をおすすめする事業所のケース | 技能実習をおすすめする事業所のケース |
|---|---|
|
|
事業者様においては、外国人介護人材の採用計画によって、特定技能と技能実習のどちらで外国人の介護人材を雇用するべきか、変わってきます。採用計画に照らし合わせて、それぞれのメリットとデメリットを十分に把握したうえで、重視する点に着目して、ご判断されると良いでしょう。