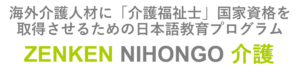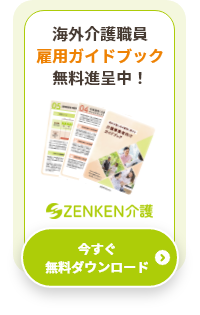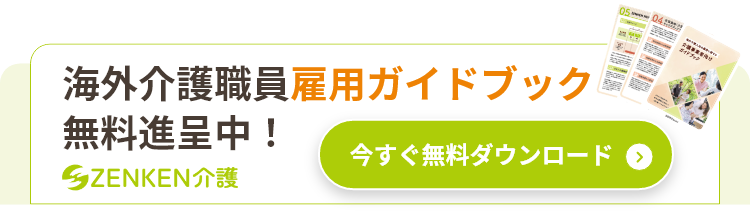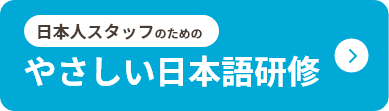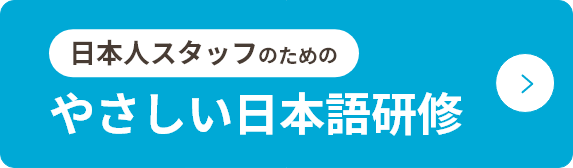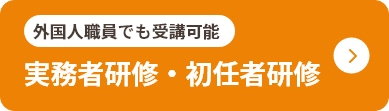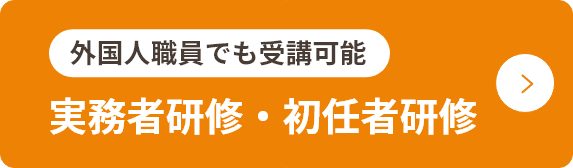特定技能・介護人材の離職率を防ぐには?
採用前の工夫と支援体制が鍵
2025.05.21

外国人介護人材の受け入れが広がる中で、多くの施設が「人手不足の解消」や「現場の活性化」といった効果を実感しています。一方で、「採用しても定着しない」「早期に離職してしまう」といったお悩みを抱える施設も少なくありません。
採用がゴールではなく、「いかに現場で活躍し、長く働いてもらうか」、この視点がますます重要になってきています。
離職の背景には、雇用条件や業務内容に対する認識のズレ、言語や文化の違い、生活面での不安など、さまざまな要因があります。しかしこれらは、採用前の工夫や、入国後の支援体制によって大きく改善できるポイントでもあります。
今回は、外国人介護人材の離職率の状況や定着につなげるための工夫や支援体制を整理するとともに、Zenkenが登録支援機関として提供する実践的なサポートをご紹介します。
「せっかく採用した人材に長く働いてほしい」「現場で安心して力を発揮してもらいたい」そうお考えの施設関係者の皆さまに、お役立ていただける内容です。
外国人介護人材の離職率から見える“定着”の実態と支援の必要性
外国人介護人材の定着については、「すぐ辞めてしまうのでは」と不安視する声もありますが、制度別・支援体制別に見ると、実際には定着率が高いケースも多く見られます。
出入国在留管理庁が公表した令和4年度のデータによると、特定技能制度で就労する介護分野の外国人材の離職率は10.6%であり、同年度における日本人介護職員の離職率(14.4%)を下回っています。
| 区分 | 離職率 |
|---|---|
| 日本人介護職員(令和4年度) | 14.4% |
| 外国人介護人材(特定技能・介護分野・令和4年11月末) | 10.6% |
出典:
日本人介護職員:公益財団法人 介護労働安定センター「令和4年度 介護労働実態調査」
外国人介護人材(特定技能):出入国在留管理庁「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議資料」
このことは、適切な制度設計と支援体制の下であれば、外国人材も高い定着率で働き続けることができることを示しており、受け入れ側の体制づくりが定着成功のカギであることを裏付けています。
外国人介護人材の離職理由の傾向
外国人介護人材が職場を離れる理由には、個人的な事情に加えて、受け入れ側の環境や支援体制の不備が影響している場合が多くあります。
たとえば次のような要因が、離職のきっかけとして多く見られます。
職場内での人間関係
日本人職員とのコミュニケーションギャップ、文化的なすれ違いなど人間関係が精神的負担になるケース。
生活面の不安
住居・行政手続き・銀行手続き・・地域社会とのつながりなど、日本での暮らしに適応できないまま孤立するケース。
業務内容と期待のギャップ
面接時に聞いていた内容と、実際の仕事の負担や介護の業務内容に乖離があり、「想像と違った」と感じてしまうケース。
日本語の壁
日常会話はできても、医療・介護用語を含む業務上の日本語に不安を感じ、業務上のミスやストレスが重なるケース。
これらの離職理由は、採用時の説明の丁寧さや入職後の支援体制によって、防止できる余地は十分にあります。
支援の質が定着を左右する
外国人介護人材が安心して働き続けるためには、就業後の生活や職場環境への適応を支える体制が整っていることが重要です。
たとえば、以下のような支援があることで、本人の不安やストレスを軽減し、結果として定着につながりやすくなります。
住まいの確保や生活インフラの整備支援
支援内容の例として、住居の手配、携帯電話・銀行口座の契約、公共交通機関の案内などが挙げられます。
日本語学習の継続支援
介護現場では専門的な用語が多く使われるため、日常会話以上の語学力が求められます。継続的に日本語が学べる環境の整備や教育支援を実施することが大切です。
定期的な声かけや相談機会の提供
相談窓口やメンターを設けることにより、不安や悩みを一人で抱えずに済む環境があることで、外国人介護人材の精神的な安定につながります。
職場との橋渡しや文化的なギャップの調整
日本人職員向けに「やさしい日本語研修」や「異文化理解研修」を実施したり、イラストや動画を使用したりしてコミュニケーションを取るなどの工夫することをおすすめします。
特定技能制度においては、登録支援機関が上記のような支援を担う役割を持っており、こうした取り組みが外国人材の定着を後押ししています。支援の内容が充実していればいるほど、本人が「ここで働き続けられる」という見通しを持ちやすくなります。
離職のリスクを減らすには採用前の「認識合わせ」が重要
外国人介護人材の早期離職の大きな要因のひとつに「採用前の認識のズレ」があります。仕事内容や勤務条件、文化的な違いへの理解不足が、入職後の不満や混乱を招き、結果として短期離職へとつながるケースは少なくありません。
事前説明の明確さが離職を防ぐカギに
近年、特定技能制度や外国人雇用に関する解説動画やセミナーでも強調されているように、採用前の丁寧な情報提供が離職防止に極めて効果的であることが指摘されています。中でも重要なのは、以下のような点を曖昧にせず、具体的に説明することです。
- 給与や賞与、手当の支給内容とタイミング
- 勤務時間、残業の有無、夜勤の頻度
- 食事・入浴・排せつなど介護の実務内容
- 配属先の人数構成や同国籍スタッフの有無
- 研修やOJTの有無とその期間
「一通りやってもらう予定です」「場合によっては夜勤も」などの抽象的な説明は、後に誤解や不信感を招きやすくなります。
資料・通訳・動画など多様な手段で“伝わる”工夫を
外国人材の多くは、日本語がある程度理解できても、専門用語や間接的な言い回しには不慣れな場合が多いです。そのため、次のような伝達手段の工夫が重要です。
- 写真付きや図解入りのやさしい日本語資料
- 母国語翻訳つきの雇用契約書・説明動画
- 通訳者や支援員を交えた三者面談
- 施設での1日の流れを紹介する動画コンテンツ
こうした手段を用いることで、単に「伝える」ではなく、「伝わる」「理解してもらう」説明が可能となり、安心感と納得感が生まれます。
文化・宗教的背景にも触れた配慮が信頼関係の第一歩
離職の背景には、業務内容だけでなく、生活面や宗教・文化的な習慣への配慮が不足していたことによるストレスもあります。たとえば以下のような点に事前に触れておくことが重要です。
- 食事に関する制限や配慮(例:ハラール、ベジタリアン)
- 宗教的な祈りの時間や服装
- 生活上の不安や質問に対する相談先
相手の文化背景を尊重した説明や質疑の場を持つことで、信頼関係の構築にもつながり、定着意欲の向上にも貢献します。
「将来のビジョン」を共有することが定着促進に有効
外国人材が安心して長く働けるかどうかは、「将来の見通しが持てるかどうか」に大きく関係します。たとえば、以下のようなキャリアパスの説明は、特に有効です。
- 介護福祉士国家試験に合格すれば「在留資格・介護」へ変更でき、長期就労が可能になる
- 日本語のレベルアップ支援があり、試験合格を目指せる体制がある
- 将来的には介護チームのリーダーやOJT担当者としても活躍できる可能性がある
このように、単に「今の仕事」だけでなく、「未来のキャリア」が描けるようにすることが、離職を防ぎ、定着を促進する大きな要素になります。
登録支援機関の支援体制が離職率を大きく左右する
特定技能制度において、外国人介護人材が安心して働き続けるためには、就業先の環境だけでなく、登録支援機関のサポート体制が非常に重要な役割を果たします。
登録支援機関は「単なる事務代行」ではない
登録支援機関は、特定技能人材の受入れに際して、出入国管理庁から委託された「支援責任」を担う存在です。しかし一部では、名義上登録されていても、実態として十分な支援を行っていないケースも見受けられます。
本来の登録支援機関の役割は、書類提出や手続き代行といった事務業務だけではなく、就業前後の生活・就労支援を通じて、外国人材の定着をサポートすることにあります。
「顔が見える支援員」の存在が孤立感を和らげる
登録支援機関の中には、形だけ登録されていて実質支援が行われていないケース(「名義貸し」「形式的支援」など)も存在します。
その場合、外国人材は「困ったときに誰に相談していいかわからない」「支援担当者に会ったことがない」という状態になり、心理的に孤立しやすくなります。
また、「日本語が十分通じず、困っても伝えられない」、「生活上のトラブルを一人で抱えてしまう」といった生活上・精神的な孤立感があります。
こうした孤立を防ぐには、「困ったときに母国語でも連絡できる顔が見える支援員」の存在が非常に大切です。定期的に面談し、通話アプリや通訳ツールなどで気軽に相談できる体制があることで、小さな不安やストレスを早期に解消することができます。
日本語学習の支援は“定着”と“キャリア形成”の要
介護の現場では、単なる日常会話だけでなく、医学的・専門的な言葉や敬語・接遇表現が求められます。
日本語への不安があるまま現場に入ると、業務上のミスや誤解を招き、本人にとっても大きなストレスとなります。また、特定技能から「介護福祉士国家資格」へのステップアップを目指す場合の日本語教育支援も重要です。そのため、入国後も継続的な日本語学習を支援する体制が、定着と将来展望の両面から非常に効果的です。
Zenkenは、登録支援機関として、制度上義務づけられた10項目の支援に加え、実践的な安心サポートを提供しています。
主な支援内容
- 入国前の生活オリエンテーションと雇用条件の丁寧な説明
- 空港送迎、携帯・銀行など生活インフラの手続き支援
- 生活に関する質問・相談を母国語で対応できる正社員の常駐
- 介護福祉士国家試験合格を見据えた日本語教育プログラムの提供
- 定期面談、職場訪問、通話アプリを活用した継続的なフォローアップ
支援員が単なる“管理者”ではなく、「困ったらすぐに話せる存在」であることが、外国人材の安心感と信頼につながっています。
外国人介護人材の受入れを成功させるためには、採用前の認識合わせだけでなく、採用後の支援体制を誰がどう担うかが極めて重要です。
Zenkenでは、面接〜入国〜定着〜資格取得までを一貫してサポートし、介護現場と外国人材の双方が安心して長く働ける環境づくりを支援しています。
特定技能介護の外国人材の採用をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
長期定着を実現するZenkenの人材育成と支援の取り組み
外国人介護人材の安定的な定着と、介護現場での即戦力化を実現するために、Zenkenでは単なる人材紹介にとどまらない“成長支援型のマッチング”を行っています。
国家資格取得を目指す人材を厳選してご紹介
Zenkenが紹介する外国人介護人材は、介護福祉士国家資格の取得を本気で目指し、日本の介護施設で長期的に働く意欲のある方々です。
特定技能制度のもとで5年間働くことが可能ですが、その期間を単なる就労とするのではなく、介護福祉士という国家資格を取得し、在留資格「介護」へ切り替えることを前提とした人材育成と紹介を行っています。
採用後すぐに辞めてしまう人材ではなく、キャリアビジョンを持ち、努力を続けることができる人材を見極め、厳選してご紹介することで、受け入れ施設にとっても安心して育成できる関係性を築くことが可能です。
入国前から始める“育成型”の日本語教育支援
Zenkenでは、介護施設との面接を経て外国人材に内定が出た後、入国までの期間を単なる“待機期間”とせず、学習期間として活用しています。
この期間に、将来働く介護現場で日本語に困らないよう、介護の専門用語を含む実践的な日本語教育を行い、入職後すぐに現場に馴染めるようサポートしています。
こうした「入国前のブランク解消」と「語学力の底上げ」は、外国人介護人材の就労初期の不安や戸惑いを大幅に軽減し、スムーズな職場適応と早期定着にもつながっています。
国家資格取得を見据えた“3年計画”の学習支援
Zenkenでは、外国人介護人材が入国後も学び続け、介護福祉士国家資格の取得を目指すための日本語教育プログラム「ZENKEN NIHONGO 介護」を提供しています。
このプログラムは、介護現場で実際に使われる表現や語彙を中心に、日本語力を段階的に高めることを目的とした学習支援で、以下の特徴があります。
- 動画による自主学習(1本10分程度)+オンラインライブ授業のコホート型学習
→ 学習者同士で進度を揃え、仲間とともに学ぶことでモチベーションを維持
- 毎日の動画レッスンと復習課題(1日30〜60分程度)
→ 忙しい現場のスケジュールの中でも無理なく継続可能
- 介護現場での実務経験がある日本語教師が担当
→ 介護現場に精通した日本語教師の指導により、単なる語学教育ではなく、介護福祉士取得に必要な専門的な日本語力までを視野にサポート
- アウトプット重視のライブ授業
→ 発表・ディスカッションを通じて、学習内容の定着と応用力を養成
このように「ZENKEN NIHONGO 介護」は、働きながら学ぶ外国人材にとって、日常業務と両立可能な実践的なプログラムです。単なる言語習得を超えて、介護福祉士としての国家資格取得に向けた“3年計画”の一環として位置づけられています。
離職率を下げるための3つの見直しポイント
前述の通り、外国人介護人材の離職を防ぐには、採用後のフォローだけでなく、受け入れ体制そのものを見直すことが欠かせません。ここでは、離職率を下げるために、事業者側が今すぐ確認すべき3つのポイントを整理します。
1.雇用条件・業務内容の説明は正確か?
外国介護人材の早期離職の一因としてよくあるのが、「聞いていた話と違う」というミスマッチです。これは、雇用条件や業務内容の説明が不十分だったり、本人が正しく理解できていなかったりすることが背景にあります。
- 勤務時間・休日・夜勤の有無は明確か?
- 介護業務の具体的な内容(入浴・排せつ・食事介助など)は事前に伝えているか?
- 通訳や母国語資料など、“伝わる手段”で説明しているか?
離職を防ぐためには、「伝えたつもり」ではなく、“本人が理解した”という状態をつくることが重要です。
2.登録支援機関は、生活・学習・精神面まで支援しているか?
外国人材が離職する大きな要因のひとつが、仕事以外の“生活不安”や“孤立感です。
- 入国後の生活インフラ(住居・銀行・スマホなど)の支援は十分か?
- 日本語の上達を支援する体制があるか?
- 定期的に話を聞いてくれる“顔の見える支援員”がいるか?
支援機関が形式的な対応しかしていない場合、問題が深刻化する前に発見されず、突然の離職につながることがあります。支援の「質」は、離職率に直結する重要なファクターと言えるでしょう。
3.国家資格取得までを見据えた支援が用意されているか?
外国人材の中には、「日本で介護福祉士の資格を取り、長く働きたい」という意欲を持った人も多くいます。しかし、職場にそのステップを支援する体制がなければ、将来が見えず離職を選ぶケースもあります。
- 実務経験3年の間に、日本語力や試験対策の支援が用意されているか?
- 資格取得に向けての声かけ・キャリア相談ができているか?
- 働きながら学べる体制(研修・eラーニングなど)は整っているか?
外国人介護人材が国家資格を取得し、長く働き続けられるようにするには、受け入れ施設側も「育成のパートナー」として、学びを支える姿勢が求められます。
まとめ
外国人介護人材の受け入れは、単なる人手不足対策にとどまらず、現場に新たな視点や活力をもたらす存在として注目されています。一方で、「すぐに辞めてしまうのでは」という不安の声も根強くありますが、離職率は“支援体制の差”によって大きく変わるのが実情です。
雇用条件の明確化や丁寧な事前説明、生活・語学面のサポート、そして国家資格取得を見据えた長期的な支援体制が整っていれば、外国人材は安定的に定着し、戦力として成長していきます。
本コラムを通じて、採用前後のプロセスや支援体制の見直しが、離職率の低減と継続雇用の鍵であることをお伝えできれば幸いです。
Zenkenは登録支援機関として特定技能介護人材の現地教育から採用、日本語教育、更には「定着」を目的とした国家試験取得まで、あらゆる課題をワンストップで解決します。「採用してもすぐ辞めてしまう…」そんな課題にお悩みの方こそ、まずはご相談ください。